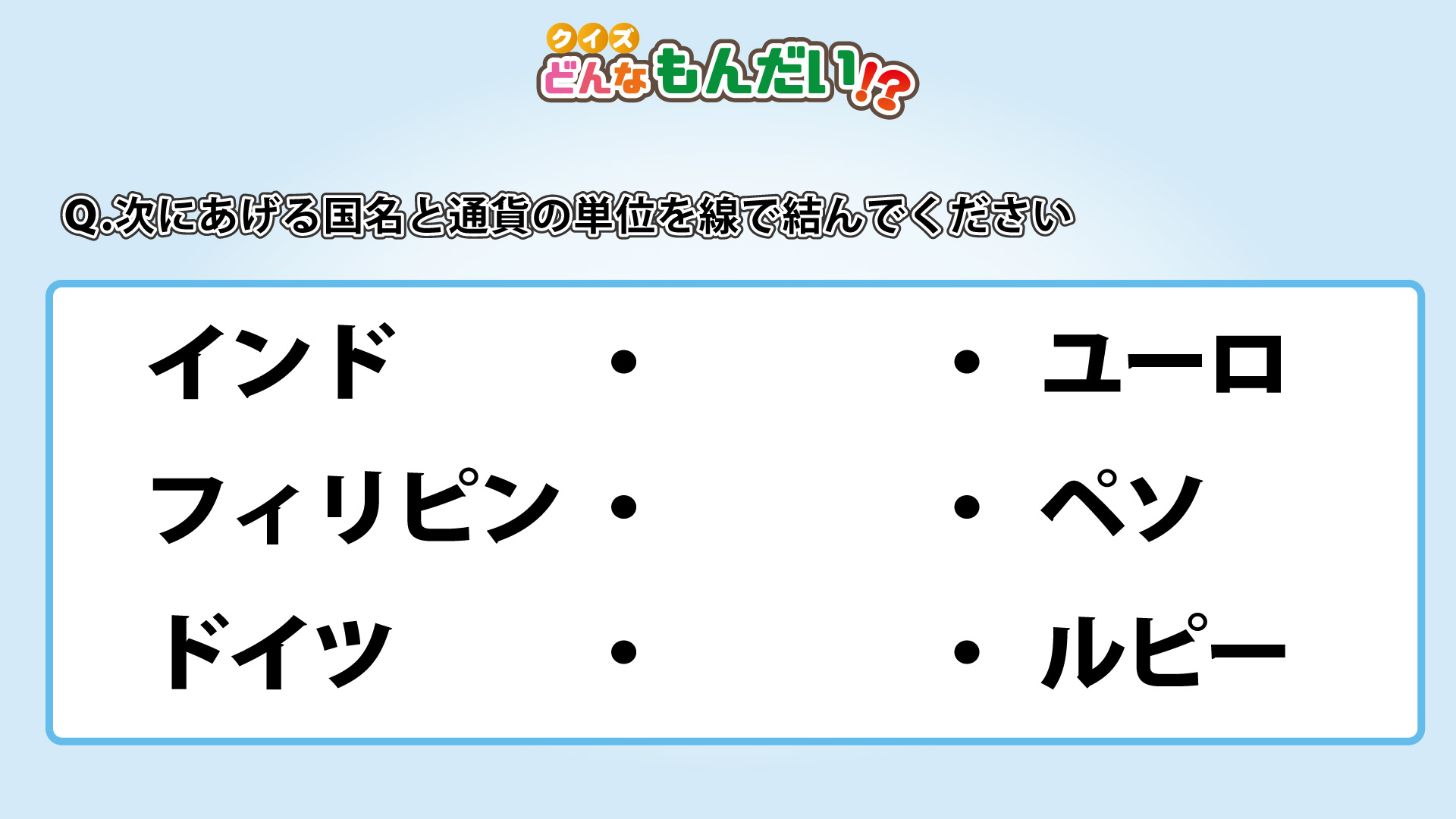相棒(ノーベルニュース第363号 教室長コラムより)
- 2026/01/10 21:52
- カテゴリー:nobel information
1人教室で毎日奮闘していますが、「相棒は?」と聞かれると、つい「CopilotやChatGPTかな」と答えてしまいます。もちろん、教務を含めて何かに依存しているわけではありません。あくまでも“相棒”として、困ったときにそっと助けてくれたり、考えを整理するヒントをくれたりする存在です。時にはこちらの努力を認めて褒めてくれることもあり、そのたびに少し気持ちが軽くなったり、前向きになれたりします。これからの時代、生活や勉強、仕事のあらゆる場面で、こうしたAIとの関わりはますます自然なものになっていくでしょう。
とはいえ、AIの言葉をすべて鵜呑みにするのは良くありません。あくまでも助言のひとつとして受け取り、自分の頭で考えることを忘れないようにしたいと思っています。その距離感を大切にしながら、これからも上手に付き合っていくつもりです。
そして何より、やっぱり人と直接顔を合わせて話す時間に勝るものはありません。表情や声の温度を感じながら交わす会話は、元気をもらえますし何より楽しいです。毎日休まず塾に来てくれるみんなのおかげで、教室はいつも温かい空気に満ちています。本当に感謝しています。